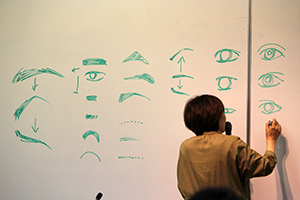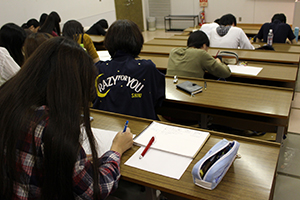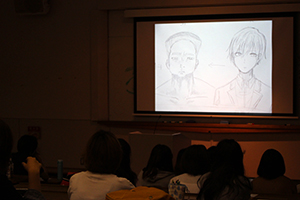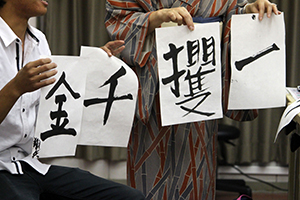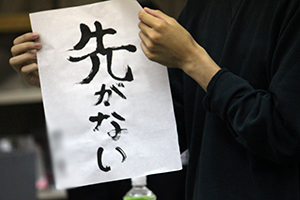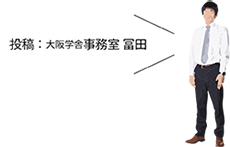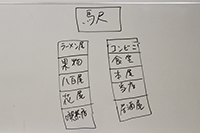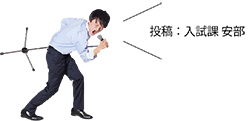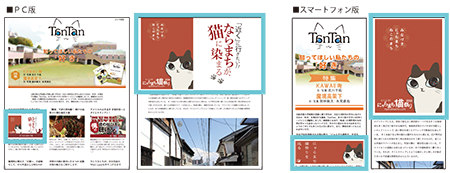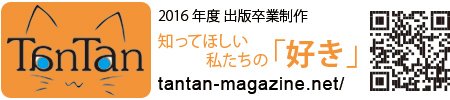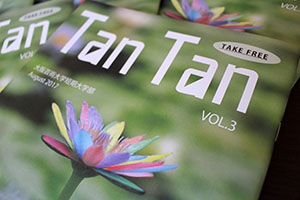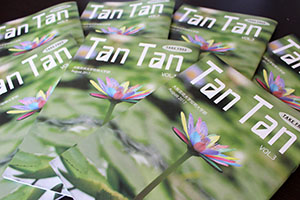三林京子先生が担当する「表現研究」で日々学ぶ学生達から、
隣接するいずみ幼稚園児たちにプレゼンツ第2弾!
10月のお誕生日会でステージを披露しました。
前回はヒーロー「テンジンジャー」の登場、そして今回は・・・。

4人の子どもたちが「ふしぎな森」に棲む動物たち
-うさぎさん、ライオンさん、くまさん、パンダさん-
と出会い、遊んだり、けんかしている時に、2匹の鬼(マリオの鬼が楽しい!)が現れて、
一人の子どもと気の弱いライオンさんを連れて行ってしまいます。


みんなが助けに向かう時に、森の「女神さま」が登場。
ライトアップも美しく、まさに女神さまでした。
いずみ幼稚園の園児たちに「いずみっこパワー」を伝授します。
出演者と園児たちが一体となった、大きな声での「いずみっこパワー!」に
鬼は逃げ出しました。


最後は学生たちから歌のメッセージを贈りました。
「友達は大切な宝物なんだよ」って。

MCの二人は、絶妙な声のトーンと笑顔で、
一瞬にして園児たちの注目をさらっていました。

学生さんたち、お疲れさまでした。
園児たちの感性による応援大歓声。
鬼さんが登場したら泣き出す園児たち。
私たちも、あの頃の感性をずっと持ち続けて、大切にしていきましょうね。


舞台のみんなは気づいたかな?
子ども役の男子が一言セリフをつぶやいた途端、園児たちが「あっ!テンジンジャーだ!」
声まで覚えてくれていたのですね。
投稿:入試課 中野
◆大阪芸術大学短期大学部 ホームページ ◆大阪芸術大学短期大学部 ブログ ◆大阪芸術大学短期大学部 休講情報WEB